|
|
||
社会情報学部は、4年間で学生一人一人に確かな力をつけて社会に送り出します。
-2005年度―
札幌学院大学 社会情報学部
|
||
■ 社会情報学部で学べることは・・・・・・。 |
||
| ◆コンピューター・グラフィックス(CG)系 ~“センス”と“ねばり”が勝負です | ||
CG制作技術をトータルに学ぶことができます。ゲーム、映画、テレビCM、パソコン雑誌などでCGのいろいろな話題を見聞きしますが体系的に学ぶ機会はなかなかありません。 |
||
コンテスト入賞楯の数々  |
CGを中心として、より幅広いITスキルを身につけるために、HTML、Java、JavaScript、を使用したWebページ制作技術も同時に学びます。作品のリアルさを競うCGコンテストでは例年高い評価を得ています。学生のセンスとねばりの成果です。 |
|
|
||
◆メディア、コミュニケーション系 ~楽しく情報発信 |
||
メディア、コミュニケーション系の講義・演習も充実しています。看板授業の1つに「地域メディア論」があります。この授業では毎週、テレビ局、新聞社、コミュニティFM(ラジオ)局など、実際にメディアの現場で活躍している方をお招きして、生の声を伝えてもらいます。 |
||
| さらに、「自ら情報を収集し、加工し、発信する」演習を重視しています。インターネットやミニFMラジオを通じて、学生自身が情報の送り手となります。送り手側を経験することは、それまでの受け身的なメディア接触に変化をもたらします。 こうした講義・演習科目を通じて、地域メディアの担い手を育成し、社会に送り出したいと考えています。テレビ番組制作会社やコミュニティFM局にインターンシップに行ったり、ケーブルテレビ局、コミュニティFM局、地方新聞社などを目指す学生が少しずつ増えています。 |
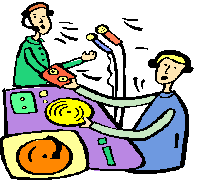 |
|
|
||
◆システム・エンジニア(SE)系 ~女子学生も頑張っています
|
||
社会情報学部をのぞくと、夜遅くまで学生達がたむろしている部屋が幾つかある事に気付くはずです。一体彼らは何をしているのでしょうか?一見するとパソコンを使って遊んでいる、あるいは雑談しているように見えますが・・・。実は、彼らはSE(システム・エンジニア)志向のゼミ生達で、仲間同士でわいわいやりながら、ゼミ研究のソフトウェア制作に励んでいるのです。SEとは様々な業務をコンピュータで行う際に必要になるソフトウェアをシステムとして設計・開発する職業の人たちの事です。皆さんは、プログラマーと言うと、部屋にこもって一人黙々とパソコンに向かっている姿を連想するかもしれません。確かに、そういった作業は不可欠ですが、実際にはチームを組んで一つのシステム制作に取り組むので、チーム内で密に議論をしながら共同作業を進める必要があります。そういった意味でプログラミング能力のみならず、コミュニケーション能力が高いこともSEの必須条件なのです。こうやって仲間同士でわいわいやっている輪の中から毎年SEとして採用される学生が巣立って行きます。自分の好きなソフトウェアを、気の合う仲間達と時間を気にしないで共同制作できるのも大学生の特権!あなたもこの輪の中に加わりませんか? |
||
◆社会調査、データ解析系 ~社会現象を読み解きます
|
||||||||
学習の柱の1つに「社会調査」があります。
「社会調査」と聞いて何を思い浮かべますか?もっともなじみがあるのは、新聞でよくみかける各種世論調査や視聴率調査でしょうか。これらはたくさんのデータを集めて分析する調査方法です。でも、社会調査には参与観察法、生活史分析、会話分析など、もっといろいろな方法があります。1年生は、そうした社会調査の基礎を学びます。続いて2年生は大学構内で、3年生は大学の外に出て調査実習を行います。自分たちの問題意識にもとづいて調査票を作成し、データを収集し、分析し、結果を報告(プレゼンテーション)します。この一連の作業で培った力は、社会に出た時に大きな力を発揮します。現在、仕事でマーケティングを担当している卒業生のMさんは、「自分の足で情報を集め、実際に社会の現場を調べる。そんな訓練が仕事に役立っています」と述べています。なお、本学部では、社会調査士資格認定機構が認める「社会調査士」資格の取得が可能です。2004年度は11名が資格申請をしました。 |
||||||||
|
||||||||
■ 社会情報学部 の教育の特徴はこれだ!! |
|||||
◆TA、SAによる少人数教育を実践しています。 |
|||||
TAとはティーチング・アシスタント、SAとスチューデント・アシスタントの略です。TAとして大学院生が、SAとして社会情報学部の学生が、演習科目にアシスタントとして参加し、よりきめ細かな授業を実現しています。
|
|||||
◆体験型教育に力をいれています。 |
|||
「からだで覚える」という言葉があります。社会情報学部では、体験を通して学ぶことを重視しており、以下のような様々プロジェクトを実施しています。 |
|||
<障がいがある方々のための学習ツール開発プロジェクト> |
|||
様々な知的障がいを抱える方々が通うウレシパ共同作業所(札幌市)と協力して学習ツールの開発を進めているゼミがあります。ゼミ生たちは、一人一人の障がいに合った学習ツールを開発し、障がいを抱えた方が自立した生活を作り出せるよう支援しています。 |
 ツールの使用実験 |
||
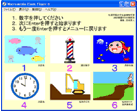 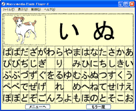 Kさんのツール Hさんのツール |
また、絵と文字とその読みを学習しているHさんのために文字をタッチするとその読みが音声で流れる50音表ツールを開発しました。大学に来て初めてパソコンに触れたゼミ生ばかりでしたが、「誰かの役に立つことができる喜びを感じた」と言います。FLASHというソフトを使用していますが、関心さえあれば誰にでもできます。 |
||
<ミニFMラジオ局「FMペポワ」の活動> |
|||
教員と学生が参加してミニFMラジオ局「FMペポワ」を運営しています。「ペポワ」という名前には、「江別の希望」という意味が込められています。現在は、週3回、お昼休みに放送しています。
|
 授業風景 |
||
<まちづくり活動への参加 ~地域の人たちと育ちあう試み> |
|||
北海道江別市のJR野幌駅北側にある商店街の一角に、空き店舗を利用したフリースペースほっとワールド「のっぽ」があります。ここを拠点に、社会情報学部の教員と学生も参加して、活発なまちづくりが行われています(この活動は2003年度に「北のまちづくり大賞」知事賞を受賞しました) 。 |
|||
 ほっとワールドのっぽHP |
主な活動は、土曜日に子どもたちと活動する「サタデーのっぽ」、月に一度、地域の人が食事をともにする「月一迷店」、地域のお年寄りの昔語りを撮影し記録する「ノッポロを聴く」などである。「のっぽ」は江別市と野幌商店街振興会から支援を受けています。まちづくり活動を仕掛ける若者主体の「まちづくりグループACE」には、学生たちも多数参加しています。地域の人々との交流を通して、学生達は多くのことを吸収し、次第に自信に満ちた表情に変わっていきます。
|
||
<インターンシップ> |
|||
社会情報学部では、希望者にインターンシップへの参加を勧めています。インターンシップとは、学生が企業や行政機関などにおいて実習・研修的な就業体験をする制度です。就業体験を通じて、日頃の学習成果を確認したり、将来の職業選択に役立ててもらおうというのがねらいです。夏休みなどを利用して2週間程度の期間で実施します。 |
|||
| ■ 社会情報学部は就職に強い!! -なぜ強いのか?- |
||
◆正解1:もちろん、どの学部よりもIT業界系に強いからです。 |
||
右の図にも明らかなように、この11年間に卒業生の21%が情報・通信系の企業に就職しています。下の表にあるように、東京や札幌にあるソフトウェア企業で、多くの卒業生が活躍しています。 |
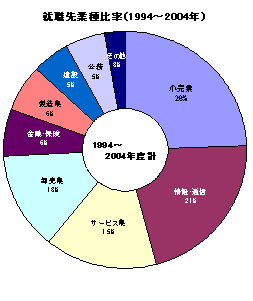 |
|
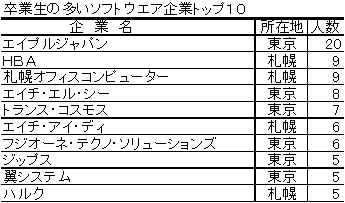 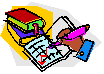 *現在、在籍している人数 |
||
◆正解2:実は、卸・小売業、サービス業、金融・保険業にも強いからです。 |
||
社会情報学部で身に付けたプラスαの力が、企業から評価されています。プラスαの力とは、第1に、エクセル、ワード、Power Pointといった基本ソフトをハイレベルで使いこなせる能力です。 |
||
◆正解3:公務員試験でも健闘しているからです。
|
||
社会情報学部学生の就職先の5.1%は公務が占めています。消防、警察、自衛隊、教員の外、各地の市町村に就職しています。これまでに、旭川市、網走市、士別市、苫小牧市、根室市、紋別市、新十津川町、釧路町、黒松内町、八雲町、生田原町(以上北海道)、青森市、五所川原市、深浦町(以上青森)、遠野市(岩手)、羽後町(秋田)などで採用され、地域社会に貢献しています。 |
||
◆もう1つの道 ~大学院への進学
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後に、就職とは違う進学という選択肢を紹介しておきます。 大学へ来てから勉学に目覚め、さらに学ぶために大学院へ進学するという学生もいます。教える側にとっては嬉しい選択の1つです。可能性は未知数です。社会情報学部では、皆さんの可能性を広げるお手伝いをします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●これまでの大学院進学先と学生数 |
群馬大学特殊教育専攻科 1人 福島大学大学院 1人 皇學館大学大学院1人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
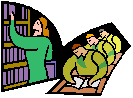 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な 内定先企業一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会情報学部の入試に、自己推薦制度が新設されました。 | ||
様々な個性をもった学生を迎え入れるために、社会情報学部では自己推薦制度を導入しました。 出願資格:高等学校を平成18年3月卒業見込みの者及び高等学校を卒業した者 日 程 B日程 出願期間 2月 20日(月)~3 月 1日(水) 必着
問い合わせ先 |
ご意見 | 札幌学院大学 |
||
|

